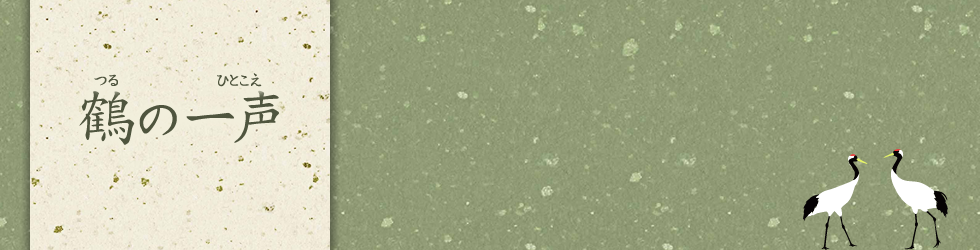杣人伝 その21
関矢こと、ツルギも今から自分がやることの意味は分かっている。
集落に居る時はそれほど感じなかったが、高校生活の中で自分たちの能力が、他の生徒のレベルと違うことはわかっていた。
それは、整備された体育館やグランドで、一定の保護の中で育まれた運動能力と、自然の険しさや厳しさの中で、命を落とす危険さえも受け入れて、極限まで鍛錬されたものの違いだろうと思った。
その差の大きさを見せつければ、そこで注目を浴びてしまう。
だから、関根校長が「野球も我慢して欲しい。体育会でも、みんなと合わせて」と言ったことの意味も理解していた。
しかし、丸山の言う通り、もうすぐ高校生活も終わり集落に帰る。
集落で暮らしていた時は、何も考えなかったが、集落を出て、こんなに広い豊かで多様性のある世界を知った。今までの自分たちの積み重ねた修練の目的はどこにあるのだろう。
そんな時、丸山から今回の話を聞き、恩ある関矢校長には申し訳ないが、一度だけ自分の力を試してみたいと承諾したのだった。
ちょうど、その時、やり投げの選手はグランドの待機場所に集まるよう、競技場の放送が流れた。
第八章 謎の少年
中央日報の藤代は、今日は日曜で非番だったので、錦糸町にある自宅マンションで久しぶりに寛いでいた。
今日は、川島たちが事務所で、山田はカメラマンの三宅と一緒に、確か国立競技場で行われる、高校の都大会の取材のはずだった。
錦糸町は俗にいう下町で、隣は両国という江戸時代から庶民の町として栄えた。
今も住宅は多いが、進学塾とか学生アパートが多いことで知られるようになった。
駅周辺もそれほど大きな建物も無かったが、山手線の秋葉原から総武線三つ目の駅で、東京までも二十分ほどで行けることから、数年前に副都心再開発が行われ、東武ホテルが出来たり、新しいオフィスビルも建つようになった。
更に昨年、川を挟んで日本一の高さを誇るスカイツリータワーが出来てからは何となく人は多くなったが、それでも下町の風情は残していた。
ひと頃、夜になると駅の西側あたりは、夜になるとロシアや中国から来た女性たちが立ち、ミニ歌舞伎町のような風情だったが、このところのロシア中国の景気回復で、それも少し薄らいだように見える。
藤代は、昼飯を食べてソファーに寛ぎ、一度見た新聞の三面四面を見ながらテレビを見ていた。
今日は、男女共にゴルフツアーの最終戦で、特に女子は賞金女王争いが熾烈になっており、今日で決着がつくというので、三時からの放映を待っていた。
時刻は二時になろうとしていた。
妻の藤子は「今日は良く晴れてくれたから、洗濯ものがもう乾いたわ」と嬉しそうな声で、ベランダの洗濯物を取り込んで、アイロン掛けの準備をしている。
藤子とは、職場の中央日報で知り合って、社の飲み会で意気投合して結婚し、既に二十年が過ぎた。
幸いに年子で長男長女に恵まれ、二人とも都内の高校に通っている。
今日は日曜だが、長男の省吾はバスケの部活の練習に行き、長女の美穂は午後から友達と出かけると言って家を出た。
藤子は、夜の銀座でも歩いていようものなら、クラブのママに見間違うほどの、社内でも評判の「いい女」で、四十を過ぎた今でも、服装次第では女子大生で通るのではないかと思うほど若く見える。
今でも、時々社内の話題に上がるほどで、藤代も悪い気はしなかった。
今は、子供が出来てから中央日報を辞めて、時々、友人の喫茶店を手伝いながらジムに通ったりしているが、適当に人前に出て、適当に仕事をするという生活が、若さを保っている秘訣かもしれないと藤代も思っていた。
藤子も、少しは外で仕事をすることでストレス解消にもなるし、これから子供たちが大学に行くときの足しになればと思って手伝っているが、日曜は家族のために休ませてもらうことにしていた。
電話がなった。
藤子が受話器を取って、親しそうに挨拶をしている。
そして、「あなた、川島さんからよ」そう言って電話の子機を持ってきた。
「よう、ご苦労さん、何かあったか」
「お休みのところ、すみません。携帯に電話したんですが」
「ああ、ごめんごめん。休みの日はモードにしてしまって、後で留守電聞くのが癖になっててね」
川島は、藤代が最後まで言うのを待ちきれないように言葉を挟んだ。
「今、山田さんから電話があったんですよ」
「山田から?確か、今日は国立競技場の高体の取材に行ってんだよな」
「そう、そうなんですが、そこで面白いことになっているらしいんですよ。それで、これは藤代さんに是非知らせなきゃって。休みだから、どうしようかと思ったんですが、知らせなきゃ絶対後で怒られると思って」
「何だよ、それ、勿体ぶらずに言えよ」
「例の少年ですよ」
藤代は、例の少年と聞いて、今年の春の大学駅伝の時の記憶が甦った。
あの後、中央日報の他の部署まで動員して探したが、結局は見つからず、夏の甲子園予選が始まると、スポーツ部はそちらの取材が忙しくなり、いつまでも幻の人探しに関わっておれず、記憶の奥に仕舞ったままだった。
「間違いないのか」藤代は、少し高揚した口調で聞いた。
「それは、僕も確かめてはいないんですけど、とにかく行ってみませんか」
「わかった、俺は、今からすぐ競技場に向かうから、山田に目を離さないように言っておいてくれ。着いたら携帯に電話すると」
電話を置くと、妻の藤子に、「ちょっと出かける。何でもいいからカジュアルな服を出してくれ」そう言って立ち上がった。
つづく