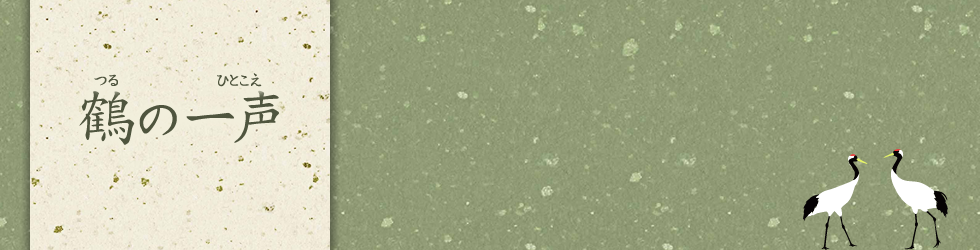杣人伝 その10
スポーツ記者として、数多くのマラソンや駅伝を観戦してきた中央日報の藤代は、いつものように吸いなれたセブンスターを指で挟み、肩肘をつきながらテレビで中継されている関東地区大学駅伝大会を観ていた。
どちらかと言うと、駅伝よりマラソンが好きな藤代だが、母校の日東大が、この駅伝の常連で、しかも、ここ数年は上位に入っている。特に今年は優勝候補として名前が挙がっている。
今日は日曜で、たまには家庭サービスで、普段の罪滅ぼしをしたいところだったが、年上の大塚に休みを譲り、山田、川島の独身組に混じっての番記者ということになっていた。
大学駅伝の記事は、ほとんど優勝した大学の最終ランナーのテープを切る写真とインタビューで占められ、後は用意されているランナーの資料、途中のタイムと順位の記録があれば済む。
現場には、現場記者と撮影スタッフがおり、その写真とインタビュー内容が送られてきたものをいち早く纏めて、決められた紙面の中で、他のスポーツ記事と割り振りして終わり。
記事の内容よりも、見出しの鮮烈さや表現力が重みを増すのがスポーツ紙だ。
今日の藤代は、記者と言うよりどちらかと言えば、大学の先輩として、後輩達の応援を決め込んでいた。
期待に反せず一区では、日東大は日体大、明治大と共に首位に並んでいた。
一区十キロの丁度中間点を第一集団が通過して、第二カメラが第一集団から三百メートルほど遅れた第二集団を映し出した。
前評判の良かった選手が第二集団に落ちていたため、カメラは暫くはその選手を道路中央サイドから迫っていた。
藤代は、その集団を追っているカメラの中に、歩道を走っている黒い影に気づいた。
走っているのではっきり見えないが、どうも黒い学生服を着た少年のようだ。
知り合いの選手がいて応援で走っているのか、ふざけて伴走しているのか、駅伝ではよく見かける光景だが、カメラが追っている間は走っているようなので、結構頑張っているし、よくあの人垣の中をぶつからずに上手く走るなと感心していた。
それも、厚い学生服を着て・・・そう思ったが、カメラの切り替わりと共に、少年の存在も藤代から消えた。
今度は、トップ集団につけた一号車のカメラが、再び首位を並走する三人を捉えた。
一緒に観ていた山田が言った。
「先輩、これで前評通り、日東が最後まで行っちゃって優勝したら、今日は先輩の奢りで祝杯をあげなきゃなりませんね」
「そうそう、日東がこれだけのメンバーが揃うことは二度とないかも知れませんよ。是非やるべきですよ。母校の為、母校の為ですよ」
川島が山田の言葉に乗った。
「おいおい、むお前たちが、俺を祝って奢ってくれるべきじゃないの」
藤代もまんざらではなさそうな顔で冗談を返した。
テレビは、解説を交えながら、首位とすぐ次のグループを交互に映し出していく。
その時、藤代は「あれっ」と呟いた。
先頭集団の二番手グループの歩道側を黒っぽい人影が並走している。
目を凝らして確認しようとしたが、もうカメラの中には無かった。
「まさかね、それは無いだろう」藤代は頭の中でそう呟いた。
次の瞬間、藤代は先頭の三人を映し出したカメラの中に、信じられない光景を目にした。
走っている、まさに先頭グループの横を、横と言っても歩道に並ぶ人垣の後ろで、見え隠れしているため、選手に気を取られていたら気づかないかもしれない。
時々、人や自転車が並走することはあるので、それほど気になることでもない。
しかし、これは藤代の頭の中で理解できない、ある筈がない出来事なのだ。
なぜならば、先ほどカメラが捉えた第二集団と一緒に映っていた人影が、今、先頭集団と並走している人物と同一人物だとすれば、約三百メートルの遅れを、どこから走り出したにせよ、大学のトップクラス、いや日本でもトップクラスの選手より速く走ったことになるからだ。
「ありえない、ありえない」心の中で何度も呟いた。
それも、どう見ても学生服みたいで、とにかく長く走れるような服装ではない。
藤代は、機器類に詳しい山田に、テレビの画面を顎を突き出して指しながら言った。
「これ、録画してるんだよな」
「もちろんですよ、後で記事書く時に必要ですから」山田は当然ですよと言いたげに答えた。
「ちょっと巻き戻せるか」
スポーツ新聞を読みながら二人の会話を聞いていた川島も、何かあったのかというような面持ちで二人に寄ってきた。
「何ですか」
「いや、ちょっと気になってな」
藤代は、自分の見間違いだろう、まさか、まさかそうだったらどうなのか整理がつかないまま答えた。
「いいですよ。今の機械は便利でね、録画しながら再生できるという優れものだから」
山田がテレビの機能から録画再生で巻き戻しを始めた。
「どの辺りまで戻しますか」
「ほんの三分前くらい迄でいいと思う」
「じゃ、早送りでっと。この辺でいいか」
独り言を言いながら、慣れた手つきで機器を操作しながら「じゃ、再生しますよっと」
画面はタイミング良く第二集団の有望選手を捉えた解説場面が映し出された。
「この辺でいいですか」
「さすが、山田先生、グッドタイミングだな」
やがて、さっきと同じように、カメラは右側面から数名の選手を捉えた。そして沿道の観客も同時にカメラに写り込んでくる。
「ここだ、あれだ!」
藤代が興奮気味に画面を指さして言った。
山田と川島が同時に、何があったのかその指の先を覗き込んだ。
そこには、確かに歩道を走る人影が写っている。
「ちょっと止めてくれ」
山田が咄嗟に再生の一時停止ボタンを押す。
「どう見ても、やっぱり学生服だよな。中学生か高校生。だが日曜に今時の学生が学生服を着るか」
静止画面を確認した後、山田が録画再生を押した。
「ああ、確かに走っていますね。学生だけど、よくふざけて走っているやつがいますよ。これがどうかしたんですか。確かによく頑張って走っていますがね」
藤代は、画面を記憶するようにしっかり見た後で「よし、元に戻してくれ」
「中継でいいんですね」山田が言う。
藤代は黙って頷いた。
つづく