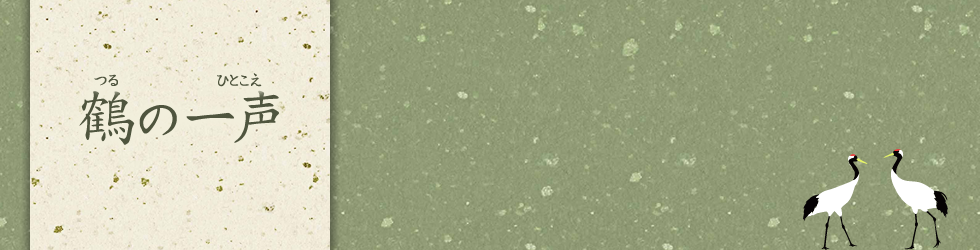杣人伝 その7
関矢がそれを感じ取ったように続けた。
「もちろん今まで、その子は学校にも通ったことも無く、はたして村人が現代社会の国語、理科数学などについて、どの程度の教育をしているかわかりません。おそらくは、先祖から受け継がれてきた掟や、忍術と言っていいのか、そういう技は教え込まれているようです。しかし、高校入試を受けても、もちろん受けるための条件もクリア出来ませんが、仮に受けたとしても、今のレベルの入試に合格することは難しいでしょう」
「そうですね・・・戸籍が無いことが一番ですが、出身中学も無いですしね」
朝倉が独り言のように呟いた。
「私も、無理な相談だとは思ったのですが、私に縁ある者という以前に、本人の意思に関係なく、そういう生き方をせざるを得なかったことや、これからの少年の人生を考えると、何とかしてあげたいと思うわけですよ」
「そうですね。変なところに預けても、こんな話を理解できないでしょうし、逆に、そういうことが公になれば、週刊誌などで見世物扱いになる恐れがありますね」
「だから、私もここ数日考えたのですよ。何かいい方法はないかと」
朝倉は、関矢が何か秘策を見出したのかと、顔を上げて関矢の顔を覗いた。
「実は、本校は私学だから、特待生入学と言う制度がありますね。特待生なら、まず入試が免除されますし、当地区以外の中学からも編入できるわけです」
「なるほど、それではスポーツ特待生として受け入れるわけですね」
二人とも、まだ完全に解決したとは思わないが、何となく可能性が出てきたことについて、お互いの目で確信し合った。
関矢は一息ついて、また真顔に戻って話を続けた。
「入学は、朝倉さんに協力して頂ければ、一連の手続き書類は何とかなります。ただ、戸籍が無いことについてはどうにもなりません。だから、その子は本校には存在しますが、日本には存在しない人間と言うことになります」
「えーと、名前は、さっきの話に出てきた、その・・・」
朝倉が言いかけると、関矢が、朝倉が聞き直すのを分かっていたように答えた。
「そう、名前は都流祁と書いて、ツルギと呼ぶそうです。その一族にかなり昔から使われた名前らしく、苗字はありません。それで、そのツルギを六所神社の神主の養子として、もちろん世間的にですよ。苗字は関矢を名乗らせることになっています」
そこまで聞いて、朝倉は覚悟したような口調で言った。
「校長、分かりました。私を信じてそこまで話して頂いた以上、何とか協力させていただきます。確かに手続きを踏まない不法はあるかもしれませんが、それによって誰かが不利になるとか迷惑を蒙るわけでもありませんし、その子の、ツルギ君の将来が開けるとしたら、先の事は先の事で考えましょう」
関谷はホッとしたような面持ちで、
「ありがとうございます。そう言って頂くと思っていました。実は、その福岡の、確か八女工業高校です。その先生には、朝倉先生のことを伝えていますので、その先生と日程を打ち合わせて頂いて、一緒にその矢部の待ち合わせ場所に行き、少年を預かってきてください」
「そして、ツルギ君をこちらに連れて来ればいいのですね」
朝倉は、心得たとばかり言葉を返した。
「いえ、福岡から一度、滋賀に行って頂き、六所村の神主と氏子総代に引き合わせることになっています。そこで、入学に必要な支度などを準備し、入学までの間、あと半月ほどありますから、少しでも中学生並みの知識や社会勉強をさせるそうです」
「なるほど、それは当校としても助かりますね。で、こちらに来てからは?」
「それは、私の家で世話をすることにしました。母もそれを望んでいますし、家内も了承済みのことです」
そして、自分に言い聞かせるように呟いた。
「本当はね、その子が本当に優秀なら、大学迄でも行かせてあげたいと思うのですが、それには戸籍の問題や、今までの生活、村の事さえも明らかにしなければならなくなり、それは村人も望んでいないようで」
「でも、そのツルギ君を社会に出したいと言っているんでしょう」
朝倉も少し納得がいかないというような口調で尋ねた。
「その村の守るべきものが守れなくなるし、殆どの人々は順応できないと考えているらしいのです。なにしろ、戦国時代から社会と隔離された人々という事ですから。取りあえず今は、私たちがしてあげられることをするだけです」
自分で踏ん切りをつけるように、関谷は朝倉に言った。
「わかりました。それでは早速、その福岡の高校の先生と話して、日程を詰めます。福岡、滋賀
東京と、一週間くらいだと思いますが、その間はよろしくお願いします」
そう言って、朝倉が立ち上がろうとした。
関谷は、引き出しからメモ紙を取り出しながら
「ここに、その八女の高校の電話番号、それに先生の携帯番号を書いています。それから、こちらが滋賀の六所神社の神主の電話番号。それと・・・これはもしもの時のために、私の実家の電話番号です。母はこちらで暮らしておりますが、この家は妹夫婦が守っており、何かあった時は世話してくれると思います」
「わかりました。私も福岡出身ですから、八女工業高校ならよく知っています。わからないことがあったら電話します」
朝倉は、そう言いながら、半身になって校長室のドアノブに手をかけた。
「朝倉さん、とにかく山の中らしい。気を付けて行ってきてください」
午後の五時くらいに校長室に入って、出てきた時は、廊下の窓越しに、幾重にも重なった帯雲が夕陽に染まり、朝倉に気合を入れているようでもあり、未知な明日を暗示しているようにも感じられた。
第三章へつづく