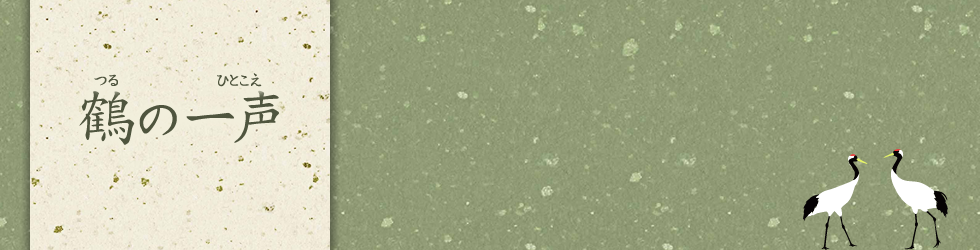互恵関係
商取引にも、いろんな形があるが、一番多いのは、売買取引関係。
稀に、お互いに売り買いがある場合もあるが、殆どの関係は、売り手と買い手と言っていい。
商品を納める会社と、それを仕入れる会社。
原料や資材業者が製造会社に、製造会社が問屋や商社に、問屋や商社がスーパーやコンビニ、百貨店に納めるという型だ。
今の日本では、95%は、納める側の立場が弱い。100%ではないのは、例えば希少なものや、人気商品など、需要供給のバランスが崩れて、物が足りないような場合は、納める側の立場が強い場合もありうるからだ。
稀に、買い手が資金的信用が無い場合も、「分けて下さい」ということになる。
戦後の復興期は、物を作る方が強い立場だった時代もある。
その後の発展で、生産能力が高まり、やがては生産過剰で、モノ余りの時代に入ると、完全に買い手市場となった。
そんな取引で、何も無い時は、お互いに必要な相手として取引を行う。もちろん、買い手の立場が強いのに変わりはないので、売り手が買い手を接待したり、取引上で便宜を図ったりするのは珍しいことではない。
問題は、欠品やクレームなどの発生時に起きる。
お互いが、相手の事情や苦労を理解していれば、そうはならないのだが、相手次第では、かなり厳しい要求があるようだ。その根源には、やはり買い手は、売り手よりも強い立場、極端な場合は上下関係と勘違いしている場合が多い。
物が足りない時代や場面を経験したことのない人間、または初めからバイヤーと言われる仕入れ担当になった人間ほど、思い違いを起こしやすい。
例えば、100円の商品に異物(人に危害の及ぶ場合は別として)が入っていたとして、九州や北海道から、すぐ上京して詫びに来いとか、今日の内に代替品を持ってこい、社員10人連れて選別に来い、1個のために、同製品1000箱を買い取りさせるなど、全くパートナーという意識もなければ、取引相手に対する思いやりもない。
そういう会社は、殆どの場合、社風がそうだし、仕事の教育はしても、もっとも大事な社員教育が出来ていないので、いずれは衰退していく。
こちらが失敗した時に、理解してくれて軽微に済まされると、「その会社に2度と迷惑かけられない、何かあったら、その会社最優先にしよう」そう思うものだ。
だから、そんな会社は発展を続ける。
以前、営業をしていた頃、同じ日に、大型スーパー2社に売り込みに行ったことがある。
1社は、バイヤーがまだ新人と思われたが、商談に来ている初老の社長と思われる人に、口の利き方も分からないのかと言いたいような無理難題を言っていた。帰られる時も、「はい、次の方」という感じ。製造の何かも分かっていない、そう思って聞いていた。
次に訪問した会社は、商談即成立ではなかったものの、課長他2名で対応してくれて、玄関まで送って「ぜひ、もう一度改良した試作品を持ってきてください」と深々と頭を下げられ、さっきの会社の後だったので、大変恐縮したことがあった。
案の定、前者は九州最大手だったが今は消滅した。
後者は、当社もその後路線を変えたので取引はないが、今も日本でも有数のスーパーとして成長している。
私は、そういう実態を見てきたからこそ、社員には、仕入れ先や物を取りに来てくれる運送会社にも、お互い互恵関係であることを忘れずに接するよう指導している。
上下関係にあると思っているところは、物が足りなくなった時に、一番先に、切られるだろう。
それよりも、あまりひどい仕打ちが続いていると、仕入れ先は、既に水面下で取引先変更に動いているかもしれない。
「いつまでもあると思うな親と物。」「いつまでもあると思うな忍耐力」